意識が飛びそうでした。いや、もしかすると本当に飛んでいたのかもしれません。
今日の会議は、本当に疲れてしまいました。
13時から開始して、気づけばもう夕方。
ごっそりと体力を奪われ、正直この後仕事をする気になれません。
最低限の仕事だけして帰ることにしました。えぇ、残業です。
とりあえずコンビニでチョコレートとコーヒーを買ってきました。
会議の議題を忘れるほどの脱線

今日の会議の議題のひとつは「来月からのキャンペーン内容を決めること」でした。
これは毎月のように取り上げられるテーマで、内容の基本構成は前回の踏襲です。
新鮮さをどう演出するか、という話が中心でした。
しかし。
ここでひとりの社員が口を開きます。
前回のキャンペーンで対応に苦労したことがあったので、そのシェアです。
「大変だったんだなー」と裏話に共感していると、ほかの社員も口を開きます。
そこから別のシェアが重なり、気づけば本題から脱線していました。
最後は「商品開発物語」を聞いていたような気がします。
いや、キャンペーンどこいった?
ある程度話したいことを話してしまうと、フッと場の空気が落ち着く瞬間ってありますよね。
そこで次の議題に進むのですが、結局、雑談で終わったような内容でした。
「意見交換の場」
「言いたいことを言い合って、日々のストレスを発散」
わかるんですけどね。
みんなストレスたまっているので、ワーっと喋ってしまいたいことは。
「最終的に判断する人が不在」の会議は、結論として「議題の持ち帰り」になりがちです。こうして次回も同じ話をすることになるのです。
会議が長引いた理由と反省

目的とゴール設定の不足
今回の会議は「意見交換の場」という曖昧な設定ではじめてしまいました。
強い意見がなければ、いつまでも話が続いてしまいます。
ファシリテーター不在
進行役がいないと、話が脱線したり発言が偏ったりして会議は長引きます。社内会議は担当者が集まるだけのことも多く、司会不在がありがちです。
準備不足や資料の曖昧さ
「資料を見ながら考えましょう」という形では、会議中に情報整理が始まり、非効率になりがちです。今作っているのが議事録なのか資料なのか、わからなくなることさえあります。
本来は、その準備の段階にもっと時間をかけるべきです。自分の意見を作り、磨き、資料に落とし込む。そのうえで意見交換を行えば、熱量の高い会議になるはずです。
逆に、そんなテンションで臨めない会議であれば、そもそもやる必要があるのか?という疑問も浮かんできますね。
「会議すること」が目的化
結局これかな、と。
本来は意思決定や共有のための会議が、「とりあえず集まる場」になってしまっています。
長くなるわけですね。
会議を短くするための改善策
議題とゴールを事前に共有する
会議招集時に「何を決める会議か」を明示しましょう。
これは大切です。
「結論が出たら即終了」でもかまわないと思います。
参加者を最小限に絞る
とりあえず呼んでいる役職者や担当者はいませんか?全員参加をやめて、必要な人だけを呼ぶのが鉄則です。
時間を区切る
「この会議は60分以内」とルールを決め、タイムキーパーを置くだけでダラダラ防止になります。オンライン会議も有効です。
チャットや書面で済ませる仕組みを作る
個人的に、これは効率的だと思います。
情報共有はメールやチャットで十分な場合が多く、「会議ゼロ化」も立派な改善策です。
無駄な会議はしない。
本屋さんに行ってみると、そういうタイトルの本すらあります。
みんな同じようなことで悩んでいるんだな・・・
共感しかありませんね笑
まとめ
会議の在り方も色々と変えていっていいのではないでしょうか?
改善を加えることで、自然と短く、生産性の高いものへと変わっていきます。
また、「会議が長いとき、主催者でなくてもできる工夫」をまとめた記事も公開しています。参加者の立場でできる工夫を知りたい方は、あわせて読んで貰えると嬉しいです。
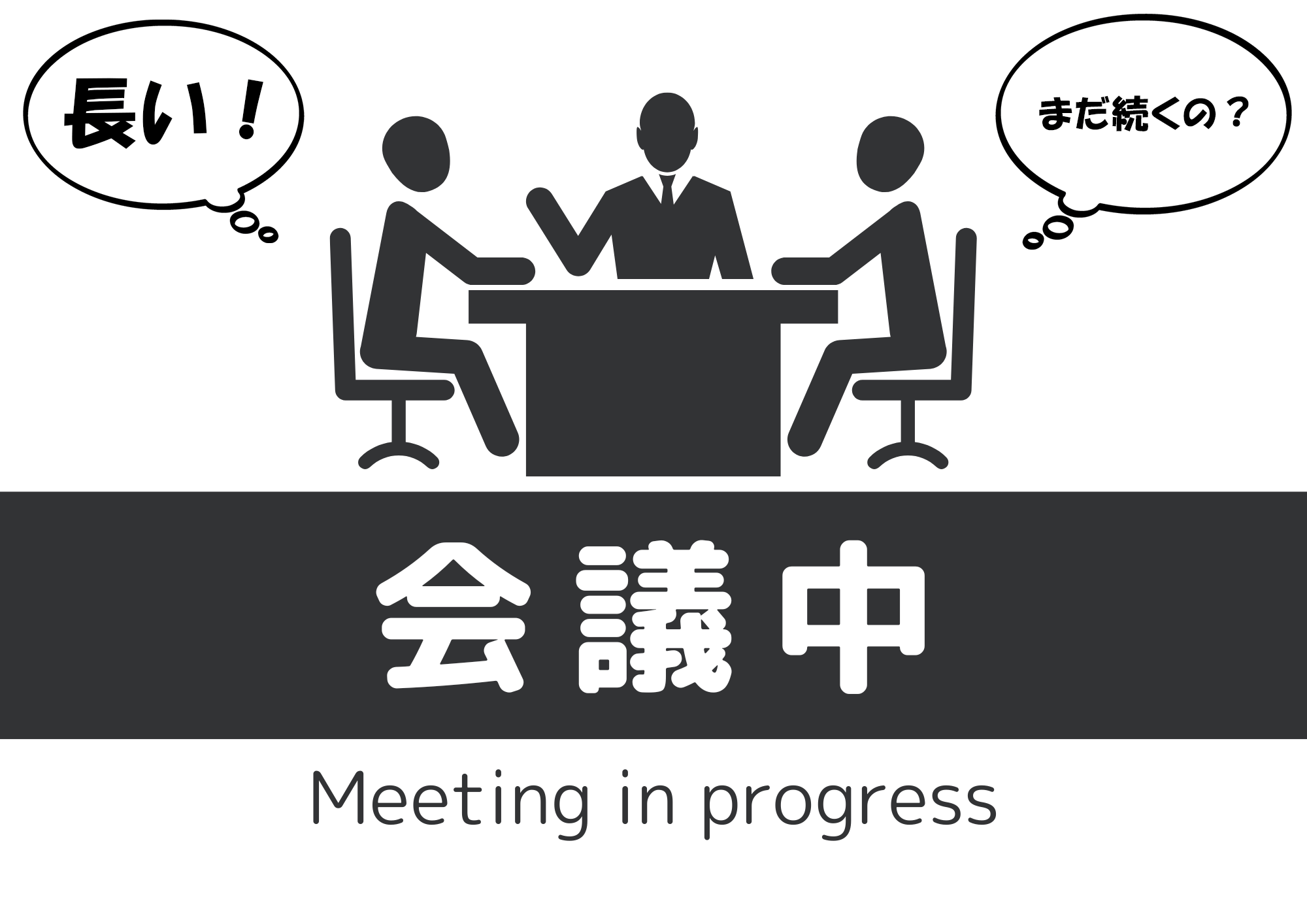


コメント