パソコン、スマホ、クラウド・・便利なツールがどんどん登場する中で、それでも手放せない道具があります。事務職、そして経理職にとってそれが「電卓」です。
新卒で事務職として働きはじめたときに電卓を購入した人も多いのではないでしょうか?
わたしは学生時代に授業で必要だったため、5,000円近い電卓を購入しました。(このお値段で学校指定の電卓でした!)
もうどのくらい使ってるんでしょうかね。
色々痛んできているんですが、いまだに、現役です。
どうして電卓が必要なのか
その理由は大きく分けて次の2つです。
・視線と手の分離ができる、唯一の道具であること
・システムへの依存を減らし、確認と思考の自由度を上げてくれること
この2点こそが、わたしが電卓を使い続ける理由であり、電卓にこだわりたいと感じる理由です。
それぞれについて、詳しくご紹介していきます。
視線と手の分離ができる
パソコンやスマホにも電卓アプリはあります。
これも便利ですが、入力時に視線を画面に集中させる必要があります。紙の資料を見ながらパソコンやスマホ画面の電卓をたたき、また紙の資料に戻って・・といった感じですね。
その点、手元にある物理的な電卓は違います。
視線は資料や伝票に置いたまま、慣れてくると電卓を見ることなく、指先だけでカタカタと計算を進めることができます。
これは、複数の数字を照合・転記する作業が多い事務職において非常に重要なポイントです。
たとえば帳票の金額をチェックしながら、電卓で計算し、すぐに記入。
パソコンで同じことをしようとすると、視線があちこちに飛び、入力ミスや確認漏れのリスクが増えがちです。
つまり電卓は、「視線と手を分離して作業を高速化できる」唯一のツールなのです。
「目」と「手」を別々に動かせるほうが、ずっと正確で早く、そして疲れにくいんですよ。
システムに頼りきらず、確認と思考の自由を持てること
Excelや業務システムには、たしかに高度な計算機能が備わっています。
自動集計や関数の便利さも、日々の業務の中で実感しています。
ただ、それでも電卓を手放せない場面があります。
それは、「この数字、本当に合ってるかな?」とふと疑問が湧いたとき。
たとえば、消費税の逆算をしたいときや、売上に対する原価率をざっくり確認したいとき。
見積もり金額に対して人件費の比率を一発で出したいときなど、「ちょっと確かめたい」「すぐに答えを知りたい」という場面で、電卓は圧倒的に効率的です。
加えて、PCとは独立したツールで計算することで、自然なダブルチェックの役割も果たしてくれます。
自動計算の結果と、自分の手で入力した結果が一致したときの安心感は、経験を重ねるほどに重みを増します。
それに、数字に強くなるにはどうすればいいか。
わたしは、「慣れた電卓を毎日使うこと」がその近道だと思っています。
売上データの確認、請求書のチェック、原価率の試算・・。
何気なく電卓を叩いているうちに、自然と数字の感覚が育っていきます。
慣れてくると、目で数字を追いながら、指が勝手に動いていることに気づくはずです。
この「手が覚える感覚」こそが、事務職に求められる「数字力」を支えているのだと感じています。
電卓には、思考を止めずに手を動かせる自由があります。
そして、画面に目を奪われず、確認に集中できる安心感もあります。
便利な時代だからこそ、自分の感覚で確かめられる道具の存在は、ますます大切になっているのではないでしょうか。

電卓は自分に合うものを
電卓とひと口に言っても、実はさまざまなタイプがあります。
キーの大きさ、押し心地、液晶の角度、桁数、税込・税抜機能の有無など、細かな違いが積み重なると、仕事のしやすさに大きく影響してくるんですよね。
選び方は、できれば12桁まで表示出来て、キーが押しやすいもの、で良いと思います。
色々機能差がありますけど、結局、押しやすいものが一番です。
わたしは薄型で軽いタイプより、少し厚みがあって指にフィットするキー感覚のあるモデルが好きです。ブラインドで打つときにもミスが減るんですよね。
「どれでも同じじゃない?」と思っていたのですが、使い込んでみて初めて、自分の手に合う道具の大切さがわかりました。
人の電卓を使うと、なんだか使いにくいんですよね。キーをたたいたときの感触が違ったり、「C」のボタンの位置が自分のものと微妙にずれていたりして。
ちょっとした違いなのに、気になるんです笑
いま事務職に就いたばかりの方がいたら、ぜひ「電卓選び」には少しこだわってほしいと思います。それだけで、作業効率も、気分も、きっと変わりますよ。
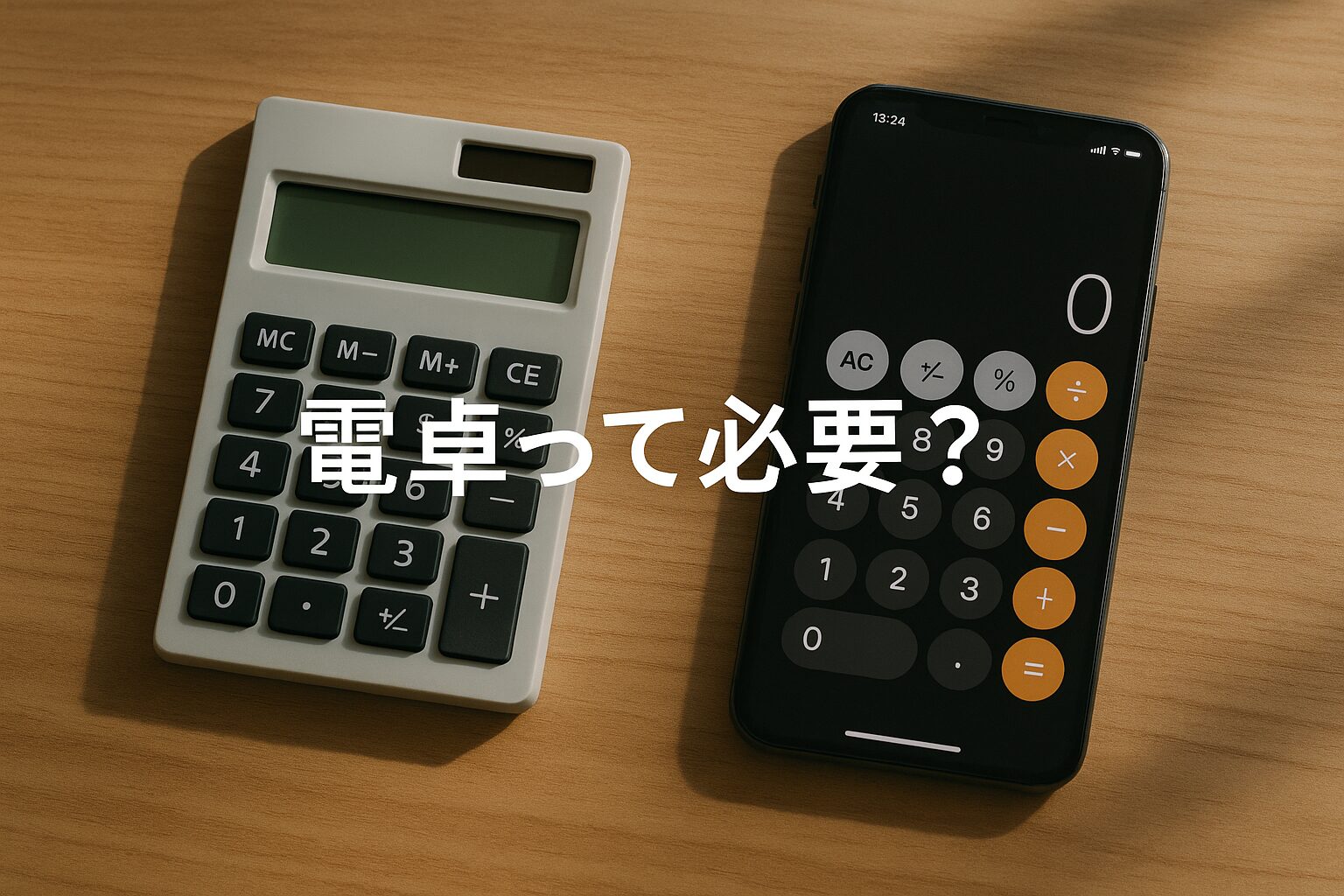


コメント