AIの勢いが止まりませんね。
どんどん賢くなり、どんどん出来ることが増えてきています。
ネット広告も、色々な会社から届くメールマガジンも、AIのことが書かれていない日はありません。
現役の経理職として、わたしはAIを学んでもいます。
自分の仕事にどういった形で活かせるだろうか、と考えてみたのですが。
今回はAI(ChatGPT)で報告書を作ってみようと思います。
経理とAIの接点
経理の仕事は、正確さとスピードが常に求められる一方で、どうしても繰り返し作業が多くなりがちです。
伝票の入力や数字の集計、会議資料の作成など、気を抜けば一日が単純作業で終わってしまうこともあります。
こうした業務は、AIとの相性がとても良い分野だと感じています。
最近では「ChatGPT」をはじめとする生成AIが、文章作成や要約、さらにはグラフの説明文まで補助してくれるようになりました。
広告やマーケティングの世界では先行して使われていますが、経理においても十分活用の余地があります。たとえば、試算表の数字を入力して「売上の増減要因を200字でまとめて」と依頼すれば、数分で報告用の草案が出てきますね。
もちろん、数字の正確性や最終的な表現調整は人間の手が欠かせませんが、それでも「ゼロから自分で書き出す」負担を減らせるのは大きなメリットです。
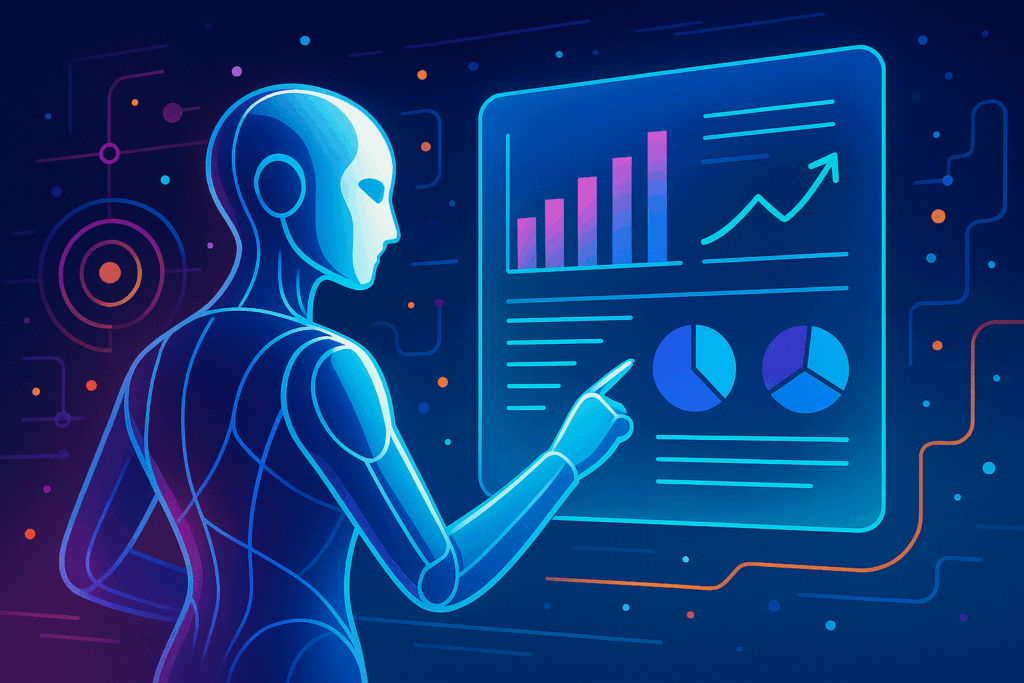
報告の準備を整える
ずは、何の報告を行うのか、ですね。
今回は「売上の月次報告」としましょう。
報告時点で積みあがった数字を使って、上司や社長に報告できる形で作ってみます。
準備としては、売上・経費・利益といった基本的な数字をそろえることから始めます。
会計ソフトやExcelから1か月分のデータを出力し、整理しておくとスムーズです。
さらに、次のような準備をしておくとAIに依頼しやすくなりますよ。
- 比較データを用意する
前月や前年同月の数字をそろえておくと、「増えた/減った」といった動きをAIが説明に反映しやすくなります。 - 注目してほしいポイントを考える
「主力商品の売上が減った」「広告費が増えている」など、強調したい点をメモしておくと、AIへの指示が具体的になります。 - 社内フォーマットを確認する
報告書が表形式なのか、グラフ中心なのか、短文まとめなのかを見直しておけば、ChatGPTに「この形式で出力して」と頼むことができます。 - 報告相手を意識する
上司向けと社長向けでは求められる粒度が違います。「詳細に数字を見たいのか」「大まかな要因だけ知りたいのか」を意識しておくと、AIにトーンを調整させやすくなります。
数字の準備だけでなく、比較・注目点・形式・相手をイメージしてからAIに渡す。
この準備次第で、AIの出力もより精度の高いものになります。
出力結果を確認・調整する
ChatGPTに依頼すれば、たしかにあっという間に報告用の文章やグラフ案が返ってきます。
けれど、そのままでは提出できません。
ここで重要なのが、出力結果の確認と調整です。
まず、数字が正確に反映されているかを確認します。
AIは便利ですが、入力ミスや解釈のズレがあると平気で違う数字を並べてしまいます。
次に、社内でよく使う用語や言い回しに合っているかを見直しましょう。
社長向けならシンプルに、上司向けなら少し詳しく――といった調整もここで加えます。
そして最後に、「自分が強調したかったポイントが盛り込まれているか」をチェックします。
もし足りない部分があれば、ChatGPTに「主力商品の減少に重点を置いて説明して」と追加で依頼すれば、より使える形に整えられます。
AIは草案を作るのが得意ですが、最終的に仕上げるのは人間の目と判断です。
この工程を通してはじめて、AIの提案が「実務で使える報告書」に変わります。
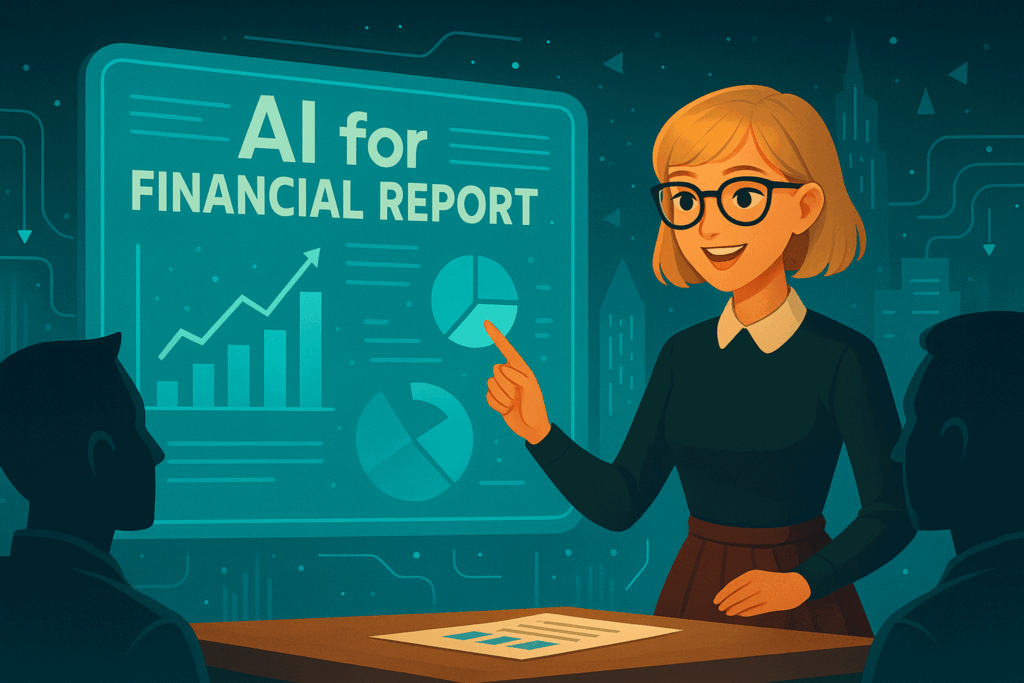
仕上げとまとめ
一度作った報告書は、報告相手に応じて、色々変更もできますね。
表を整えたり、必要に応じてグラフを差し替えたりすることで、読み手に馴染みのある形に仕上がります。ここでもChatGPTに「タイトルを3案出してください」「説明文をもう少しやわらかくしてください」などと追加で依頼することで、アレンジも簡単です。
AIで報告するコツは、「どの部分が効率化できたか」「どの指示がうまく機能したか」を整理しておくことです。これにより、次回はさらに精度の高い依頼ができます。
特にAIに与える命令文(これをプロンプトと呼びます)は重要な要素です。
AIをうまく活用できるかどうかは、どんな指示を出すかに大きく左右されます。
一度「期待通りの答え」が返ってきたプロンプトは、次回以降にもそのまま使えますし、少しアレンジすれば別の場面にも応用可能です。
だからこそ、うまくいったプロンプトは必ず記録しておくことをおすすめします。
これが、AIを実務で継続的に活かしていくための大きなポイントになります。
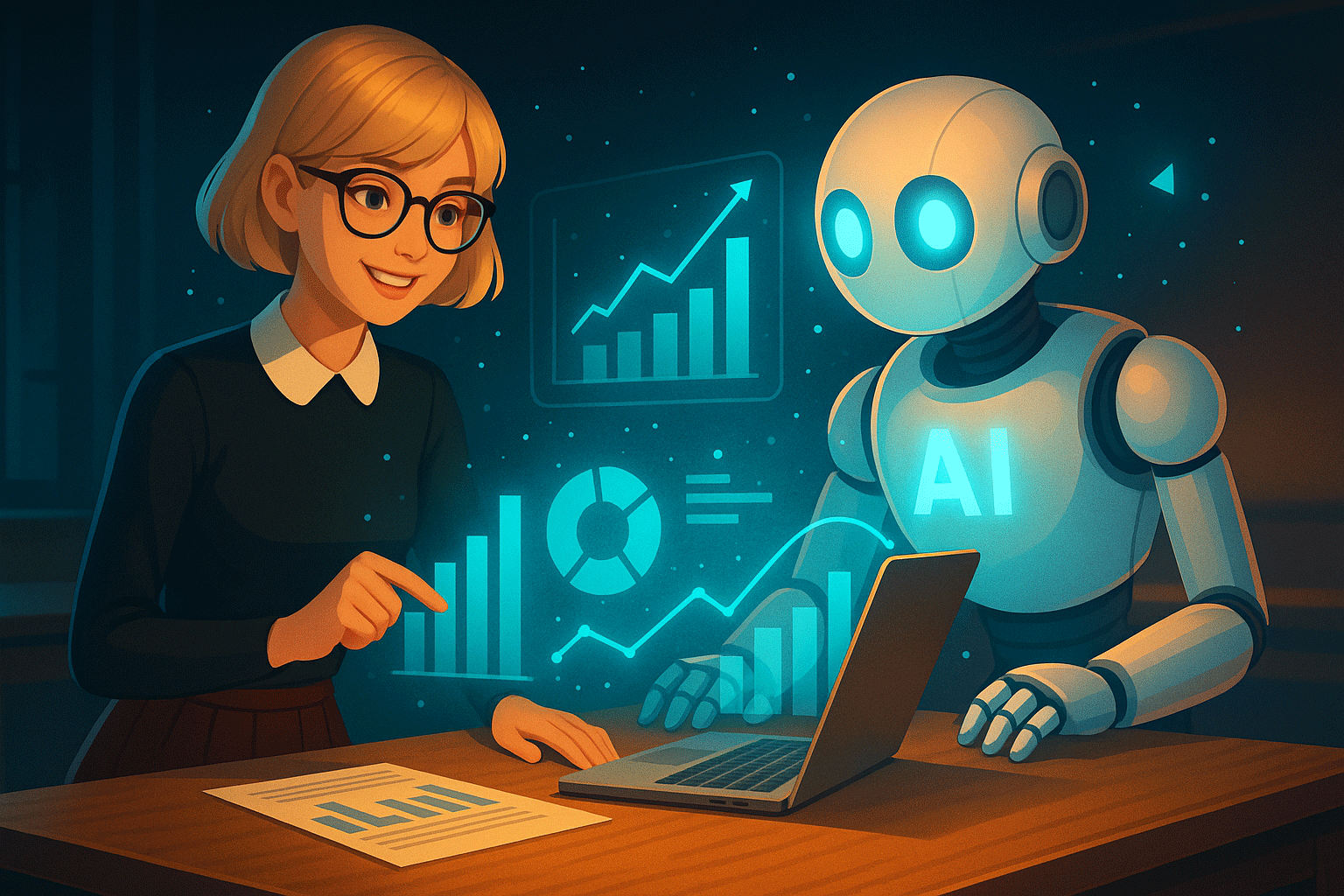


コメント