出社?在宅?
会社が荒れました。
4人しかいない部署で、1人が病欠、1人が出張、という状況で、1人がテレワークをしたのです。
よって、出勤したのは管理職1人。
わたしが出勤したときからその管理職は怒りの声を放ちまくってましたが・・・
かならず誰かいないといけない部署なので、お昼も会社でとることになるし、そもそもトイレどうすんの?って感じです。
「在宅か出社か」の議論はよく耳にしますけど、現場で起きているのはもっと切実で泥臭い問題です。
制度と現場

在宅勤務は今も人気がある働き方ですね。
採用の際に在宅OKとすると、弊社のような小さな会社でも応募が増えます。
今も多くの会社で導入されていますが、法律で保障されている有給休暇と同じように、社員にとっては「選べる働き方」のひとつとして位置づけられているようですね。
実際、在宅であれば通勤時間がゼロになり、業務に集中しやすい環境を整えることもできます。
これは本当に大きなメリットですね。
通勤ラッシュがない。
それだけでストレスがぐっと減ります。
子育てしてる方や介護されてる方にとっては仕事との両立もやりやすいです。
急な体調不良への対応といった面でも、メリットありますね。
わたしも調子悪くて出勤できなかった日に、回復してから在宅勤務をしたことあります。
しかし一方では。
出勤している現場側からすると話はまったく違ってきます。
とくに小規模な部署では「在宅で働く人の快適さ」と「出社している人の負担」が表裏一体になりがちです。
電話対応や来客対応、書類の押印や郵送業務といった「会社に人がいなければ回らない仕事」は必ず存在します。
制度の上では誰もが自由に在宅を選べても、その瞬間に必ず「穴埋め役」が生まれてしまうんですよね。
これは、有給休暇の取得をめぐる議論と似ています。
有休は権利なので、誰でも自由に取得して休めます。
でも実際に何人もが同じ日に不在となれば、業務に支障が出ますよね。
そのときに困るのは、結局その日に出勤している人です。
つまり、制度としての「正しさ」と、現場における「負担感」のあいだに、大きなギャップが存在しているんです。
たとえば冒頭のように、4人のうち3人が同時に不在となれば、残された人は昼休みですら気軽に取れません。
トイレに行くのも気を使います。
こういう小さなことってストレスなんですよね。
そこに来客対応や緊急案件が重なれば、在宅で快適に仕事をしている同僚への不満が感情として噴き出すのも無理はありません。
もちろん、在宅勤務そのものが悪いわけではありません。
問題は「制度としての自由」をどう運用するかです。
大企業であれば人員の余裕でカバーできる部分もありますが、人数の少ない部署では一人の不在が致命的になります。
これを考慮せずに「在宅OK」を一律に認めてしまうと、制度が整っているはずなのに現場では不公平感やイライラばかりが増えてしまいます。
さらにやっかいなのは、こうした不満が「制度批判」ではなく「人への不満」にすり替わってしまう点です。
在宅勤務を選んだ人が悪いわけではないんですけど・・病欠も出張も、それぞれ事情があってのことです。
でも小規模な組織では、制度の不備や調整不足がそのまま人間関係のぎくしゃくにつながってしまいます。
結果として「在宅=楽をしている」「出社=損をしている」という構図ができあがり、制度そのものへの信頼感すら失われかねません。
つまり、「制度としての在宅」と「現場のリアルな運用」には明確な溝があるのです。
制度を活かすためには、このギャップをどう埋めるかが避けて通れない課題になります。
中小企業ならではの問題点
弊社の例も書いておきます。
人数の少ない部署ほど、やはり影響が大きいですね。
大企業や大人数の部署では、誰かが不在になっても残りのメンバーでフォローできる余地があります。
しかし、数人規模の部署ではそうはいきません。
ひとりが抜けただけで、業務のバランスが一気に崩れてしまうんですよね。
たとえば電話応対。
部署に数十人いれば、誰かが受けられる可能性は高いですが、4人の部署で2人不在となれば、受話器を取る人間はほぼ固定されてしまいます。
来客対応や荷物の受け取りも同じです。
シンプルなことですが「誰かが会社に座っていること自体が業務の一部」となっている小規模部署において、在宅勤務は出勤している人の負担を増幅させます。
とれなかった電話については、折り返し対応をするため、結局仕事が増えます。
折り返して電話に出てくれるかはお客様次第ですし・・
ぶっちゃけ、残業確定ですね。
さらに厄介なのは属人化問題です。
人数が少ない部署では、どうしても「この作業はAさんしかできない」「あのデータはBさんしか分からない」といった業務の偏りが発生します。
その人が在宅勤務でオンライン対応できる場合ならまだしも、イレギュラー対応や紙書類の処理など「その場にいなければ解決できない仕事」は山ほどあるんですよね。
「今日中にこれを支払わないと・・」なんて経理のわたしが休みの日に急に言われても、外出先で会社の銀行にアクセスし、振込処理を、なんてさすがに対応できません・・。
また、人数が少ないゆえに人間関係の影響も大きくなります。
誰かが「Aさんが在宅なせいで、自分の負担が増えている」と感じれば、不満の矛先はAさんに向かいます。
本来は制度設計や業務分担の問題であるにもかかわらず、人間関係にすり替わってしまうのです。
人数が少ない部署ほど人間関係って絡んでくるんですよね。
こういうストレスは深刻なことになりやすいと思います。
つまり、小さな会社で在宅勤務を考えるときには「制度上できるかどうか」よりも「実際に残された人がどうなるか」という現場視点が欠かせないです。
大人数の職場で語られる在宅勤務のメリット・デメリットとは、まったく違う次元の課題が存在しています。
若手世代の本音
在宅勤務をめぐる議論は、世代によっても感じ方が大きく異なります。
とくに20代の若手社員は「フルリモートを希望しているのでは?」と想像されがちですが、実際の調査結果を見ると少し違う結果でした。
正直意外だな、と感じます。
法人携帯マッチングサイト「一括.jp」が20代会社員100名を対象に行ったアンケートでは、最も多かった回答が「会社や業務内容に応じて柔軟に決めたい」(24%)でした。つまり、「テレワークがいい」「出社がいい」と強くこだわっているわけではなく、そのときの状況に合わせてバランスを取りたい、という柔軟志向が主流だということです。
次に多かったのが「基本はテレワークだが、週1~2日は出社したい」(23%)と「基本は出社だが、週1~2日はテレワークしたい」(21%)。いずれもハイブリッド型を理想とする声です。
完全テレワークを希望する人は17%、完全出社を希望する人は15%と少数派にとどまりました。若い世代であっても、「フルリモート一択」ではなく、対面コミュニケーションやオフィスでの時間にも価値を見出していることが分かります。
在宅勤務のメリットについては、「通勤時間や移動の負担が減る」(36%)が最多。次いで「自宅で集中できる」(22%)、「自分のペースで仕事ができる」(20%)といった回答が続きました。やはり物理的な負担が軽減される点や、効率的に働ける点は高く評価されています。一方で、「オフィス勤務の方がよいので在宅に魅力を感じない」(27%)と答えた人も一定数いました。
不安やデメリットに関しては、「上司や同僚とのコミュニケーションが取りにくい」(28%)が最多で、「自宅では集中できない」(21%)、「ツールの不具合が不安」(18%)といった現実的な悩みも目立ちます。「評価が正当にされるか不安」(10%)という声もあり、働く場所の自由さと引き換えに、新たな課題を抱えている様子がうかがえます。
この結果から見えてくるのは、「在宅勤務=若手が求める理想の働き方」という単純な図式ではないということです。むしろ多くの若手は、出社と在宅を組み合わせる柔軟さを望んでいます。そしてその背景には、「コミュニケーション不足」「評価の不透明さ」といった不安が存在します。
つまり、若手世代にとっての在宅勤務は「自由」そのものではなく、「自由と安心を両立できる環境」であって初めて価値を持つのです。
制度だけを整えても、その環境がなければ不満や不安が募るだけ。
小規模部署の現場で起きている混乱と同じく、ここでも「制度と運用のギャップ」が浮き彫りになります。
どうすればWin-Winになるか
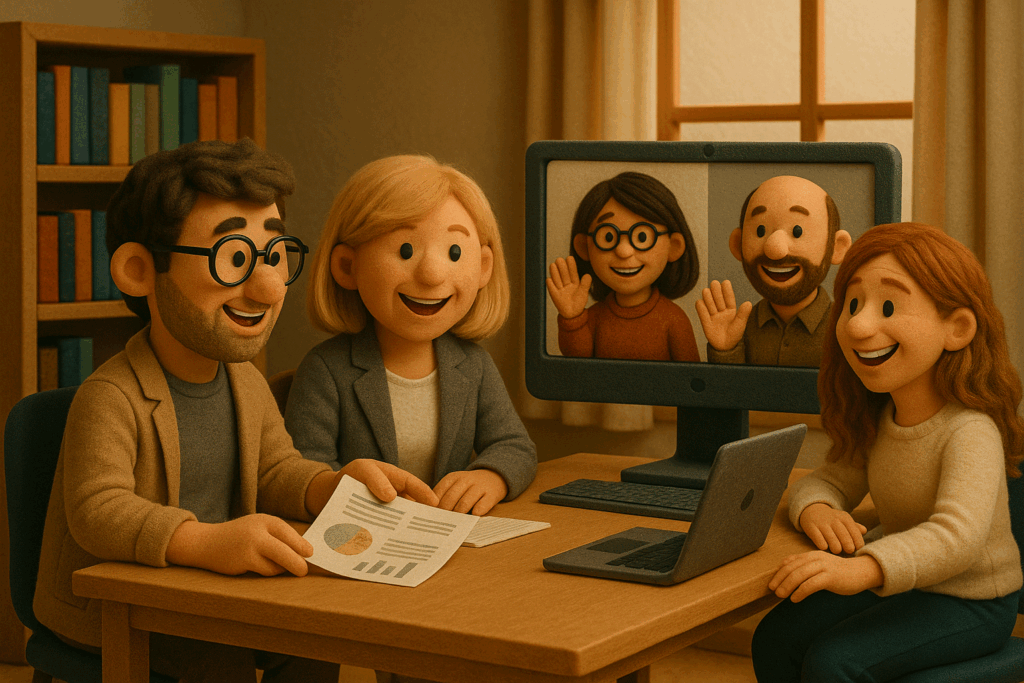
在宅勤務は社員にとって大きなメリットがある一方で、現場には負担や不公平感が生まれます。
そのギャップを埋めるためには、「制度を整える」だけでは不十分です。
肝心なのは、制度をどう運用し、現場の実情にどう寄り添うかという点です。
第一に求められるのは業務の標準化と属人化の解消です。
つまり、誰かが休んでも、あるいは在宅勤務をしたとしても、支障が出ないように業務整理をすることです。
在宅化を実現するのなら、それが可能になるように仕事を整備する必要があると思うんですよね。
全部の仕事から、家で出来ることだけを持ち帰って在宅勤務をする、という形ではなく、全体を出来るだけ在宅可能なようにデザインしなおすようなイメージです。
電話応対はクラウドを使って自宅でも会社番号が使えるサービスが普及しています。
書類処理も紙ではなく電子データで扱えば自宅でも作業可能です。
弊社はどちらも使っていますが、届いたFAXも紙と電子データの両方で確認ができるのは便利ですね。
他にも、チャットボットの導入などでそもそもの電話の数を減らす取り組みも効果があります。
問い合わせの多い項目をHPにQ&A形式で掲載したのですが、それなりに反響はありました。
電話をする側もササっと確認が出来るほうが時短になりますしね。
次に必要なのは在宅と出社のバランスを取ったシフト調整です。
偶然の重なりで「全員が不在」「ひとりしか残らない」といった事態が起こらないよう、あらかじめ調整ルールをつくる必要はあります。
人数少ない会社だと、このシフト調整が最も重要です。
直接仕事にも、人間関係にも影響しますからね。
病欠や突発的な事情までは防げませんが、出張や在宅は前もって調整できるはずです。
ここまで書きましたが、弊社では数年在宅ワークを行ってきて、取り入れたルールがあります。
それはアウトプットの量です。
在宅勤務者は今どんな仕事をしているのか、出社時よりも把握しにくいです。
ですので、在宅者には意識して「今こんな仕事してるよー」と発信してもらうようにしているんです。
具体的には社内のチャットツールで発言をしっかり行ったり、日報や月報で成果報告を詳細に行ったり、という感じです。
残念ながらそれらが不十分であったり、在宅中に連絡がつきにくい社員というのは過去に数名いました。
本人と話し合って、在宅勤務を認めないことにしますね、と通告したこともあります。
ぶっちゃけ、在宅勤務が向いてない社員というのもいらっしゃいますからね。
自宅にネットがない、という社員もいますので、「わたしはやりません」とはっきり宣言されたこともありました。
まとめ
在宅勤務は、働き方改革の象徴として広がりました。
社員にとっては通勤時間の削減や柔軟な働き方といった大きなメリットがありますし、企業にとっても採用強化や離職防止につながる利点があります。しかし、小規模な部署や人数の限られた現場では、制度の恩恵だけではなく、その影で大きな負担や不公平感が生まれていることも事実です。
今回のエピソードのように、4人の部署で3人が不在になれば、残った1人は昼食やトイレすら自由に行けない状況に追い込まれます。在宅勤務は決して悪ではありません。けれども、制度をどう運用するか、どう現場と折り合いをつけるかが問われているのです。
一方で、20代の若手社員の調査結果を見ると、「フルリモートがいい」という人は少数派で、多くは「状況に応じて柔軟に働きたい」と考えています。つまり、在宅か出社かを二者択一で捉えるのではなく、両者を組み合わせたハイブリッド型の働き方こそが、これからの現実的な選択肢といえるでしょう。
大切なのは、制度と現場のギャップを埋める工夫です。業務の属人化をなくすこと、シフトを前もって調整すること、ツールを導入して業務をオンライン化すること。そして何より、在宅を選んだ人も出社した人も「お互いの事情を理解し、感謝の気持ちを持つ」ことが欠かせません。こうした積み重ねがあって初めて、在宅勤務は「不満の種」ではなく「働きやすさの柱」として根づいていきます。
出社か在宅か。
その答えはどちらかに決めることではなく、現場の状況に合わせてバランスを取ることです。法律や制度は大枠を示してくれますが、最終的に現場を回すのは人であり、日々のコミュニケーションです。
あなたの部署では、在宅勤務と出社のバランスはどうなっていますか?
もしも偏りや不満があるのなら、制度そのものではなく、その運用や仕組みにヒントが隠れているのかもしれません。

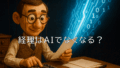

コメント